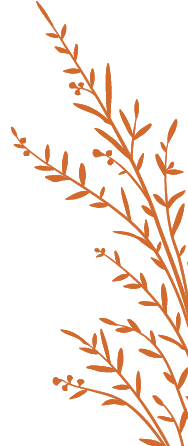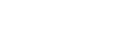港北区民俗芸能保存協会


鳥山町囃子保存会
江戸時代後期の天保年間から約180年の歴史を有しています。明治から大正にかけて矢澤七百三(なおぞう)という笛の名人がおり、近隣の村や保土ヶ谷方面からも多くの弟子が稽古に来たそうです。残念ながら昭和11年に57歳の若さでこの世を去りましたが、その技は多くの弟子により受け継がれました。昭和50年頃メンバーが4名に減り存続が危ぶまれましたが、町の有志18名が発起人となり新たな連中12名を加えて保存会を設立しました。

横浜興禅寺雅楽会
© 港北区民俗芸能保存協会・港北ふるさとテレビ局
雅楽は今から1,400年以上前に朝鮮半島、中国大陸から遣唐使により仏教とともに伝わり、平安時代に日本独自の優美な雅楽として完成したと言われる伝統と歴史的価値がある音楽です。宮廷、貴族社会だけでなく、大阪四天王寺、奈良興福寺などの寺院も伝統を守ってきました。横浜興禅寺雅楽会は、明治の中頃より100年以上にわたり継承され、かつては農民雅楽的な会だったと言われています。

菊名囃子連

昭和59年、地元の長老から菊名囃子の復活を依頼され、菊名の若手や子供たちが集まって稽古を始めました。昭和61年に菊名東口商栄会の協力で太鼓を奉納していただき、以来、地元のお祭りやイベント等でお囃子を披露しています。当初は大人の囃子と子供囃子は別々に活動していましたが、平成26年から一緒に活動を始め、名前も菊名囃子連と改めました。
新羽はやし連
江戸神田囃子を源流とするお囃子で、200年以上継承されてきました。笛、大太鼓、締太鼓、鉦(かね)の五人囃子に、舞い手が加わります。昭和20年から40年に全盛期を迎えましたが、その後衰退し、一時は消滅寸前になりましたが、近年になり再び活動を望む声が増えたため復活しました。地元の神社の祭礼や、介護施設での演奏などの活動を行っています。

日吉はやし連
日吉を中心に活動しています。日吉神社の夏の例大祭では、囃子を演奏しています。囃子連としては珍しく、組み太鼓も扱っており、創作太鼓の曲も演奏します。

綱島囃子保存会(現在休会中)
幕末の頃、綱島の人が江戸囃子を取得し、アレンジを重ねて現在の綱島囃子が完成したと伝えられています。囃子には山の手と下の手がありますが、綱島囃子は山の手囃子です。綱島周辺では下の手囃子が多く、盛んな頃は7つの囃子連がありましたが、現在は綱島囃子だけが残っています。交通事情の悪化と神社の焼失で祭がなくなり、一時は影をひそめていましたが、祭の復活と昭和4年7月の神社の再建をきっかけに復活しました。

小机城址太鼓
平成2年、大堀町内会文化部が、小机城址太鼓と命名し発足されました。江戸前の粋と伊奈世が心情の助六太鼓を基本とし、独自の作風を研究、新曲の発表、演奏技術の向上を目指して日々活動しています。

正藤太鼓(現在休会中)
港北区新吉田西部町会で30年にわたって盆踊りの太鼓や老人介護施設での慰問演奏などを行なっています。組太鼓は、太鼓だけで色々なリズムを作りますが、高い音を出す締め太鼓、中間の音を出す桶太鼓、低い音を出す宮太鼓を組み合わせて心地よい太鼓の音を楽しみます。

大曽根夢太鼓 どどん鼓
横浜市立大曽根小学校のPTAサークルとして結成され、毎週日曜日に小学校の音楽室で練習しています。町内のお祭りや盆踊りのほかに、地域のイベントなどでも演奏しています。

和太鼓ユニット三色団子
港北区内で行われるお祭りや祝賀行事、高齢者施設などのイベントで太鼓演奏活動をしている3人組です。篠笛、鳴り物を取り入れ和楽器の楽しさを伝えています。
(写真は「風だまり」の演奏です)

岸根囃子連
岸根囃子は、港北区岸根町に祭囃子として昔から受け継がれている郷土芸能です。昭和58年に、横浜市教育委員会から横浜市無形民俗文化財保護育成団体として認定され、地域に根ざした活動を行うと共に、「ふるさと岸根」の文化遺産として次の世代に伝える取組みも行っています。
1986年と1995年にカナダのバンクーバー市、1989年と2004年にフランスのリヨン市、2007年には米国のサンディエゴ市に、また、昨年11月にはフランス・リヨン市を横浜市の国際親善訪問団の一員として訪問し、国際親善にも一役買っています。平成27年11月13日には、地域文化の振興と国際交流に貢献したことで、第64回横浜文化賞を受賞しました。